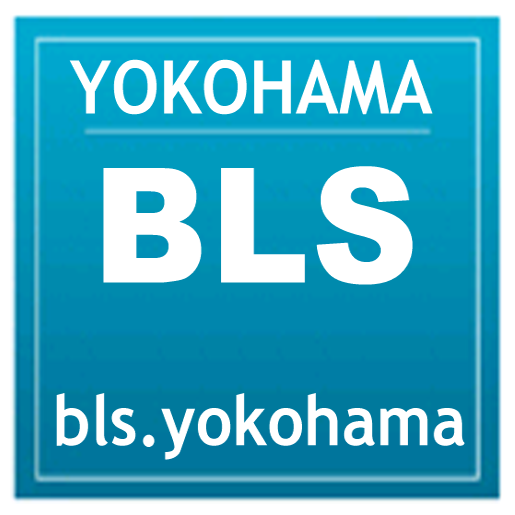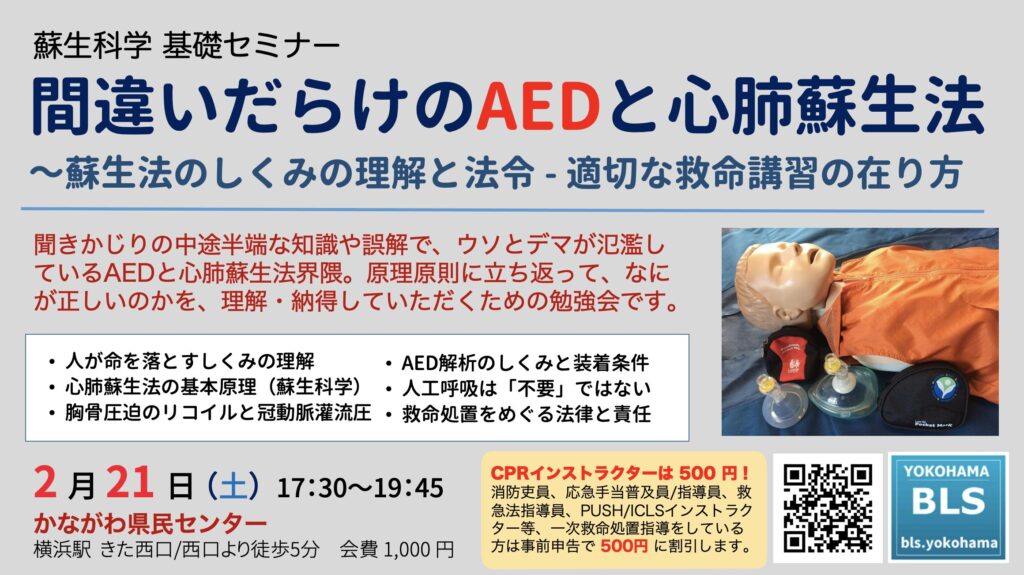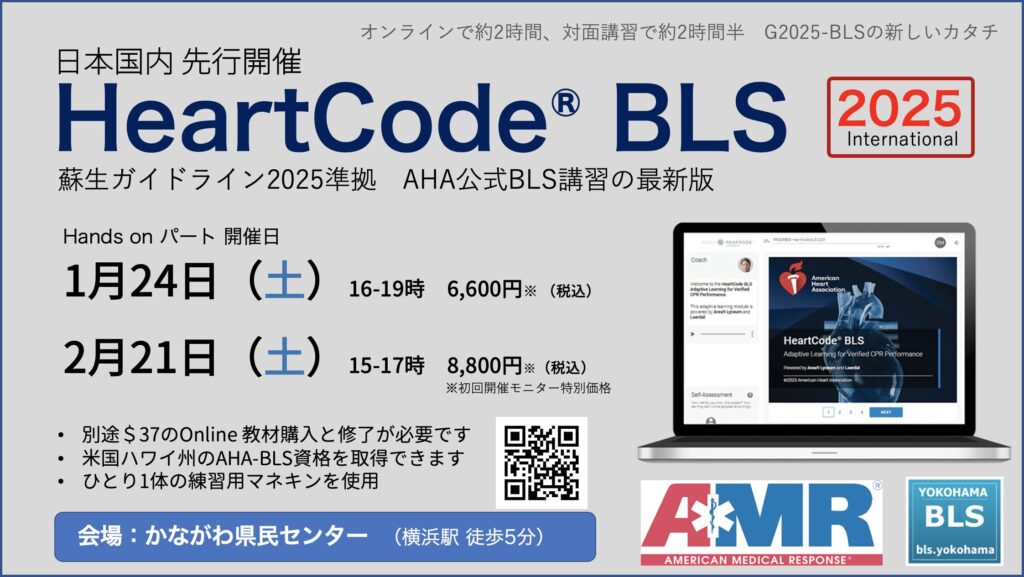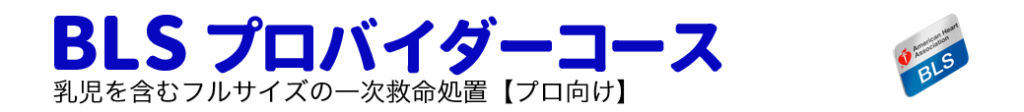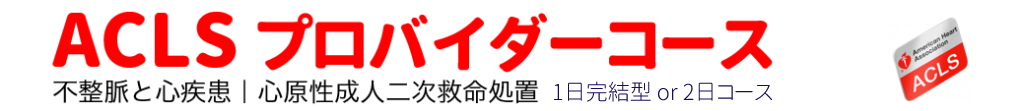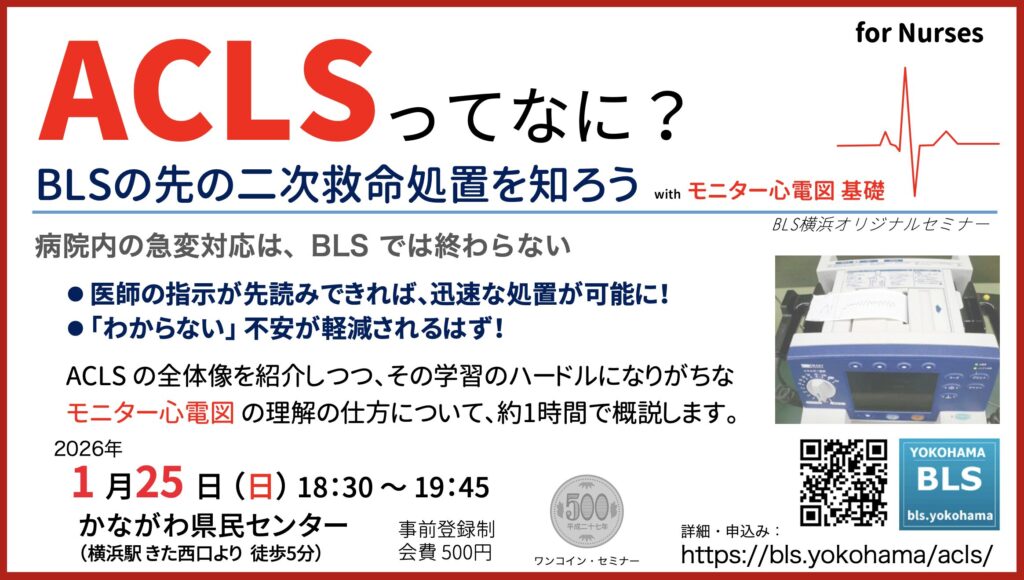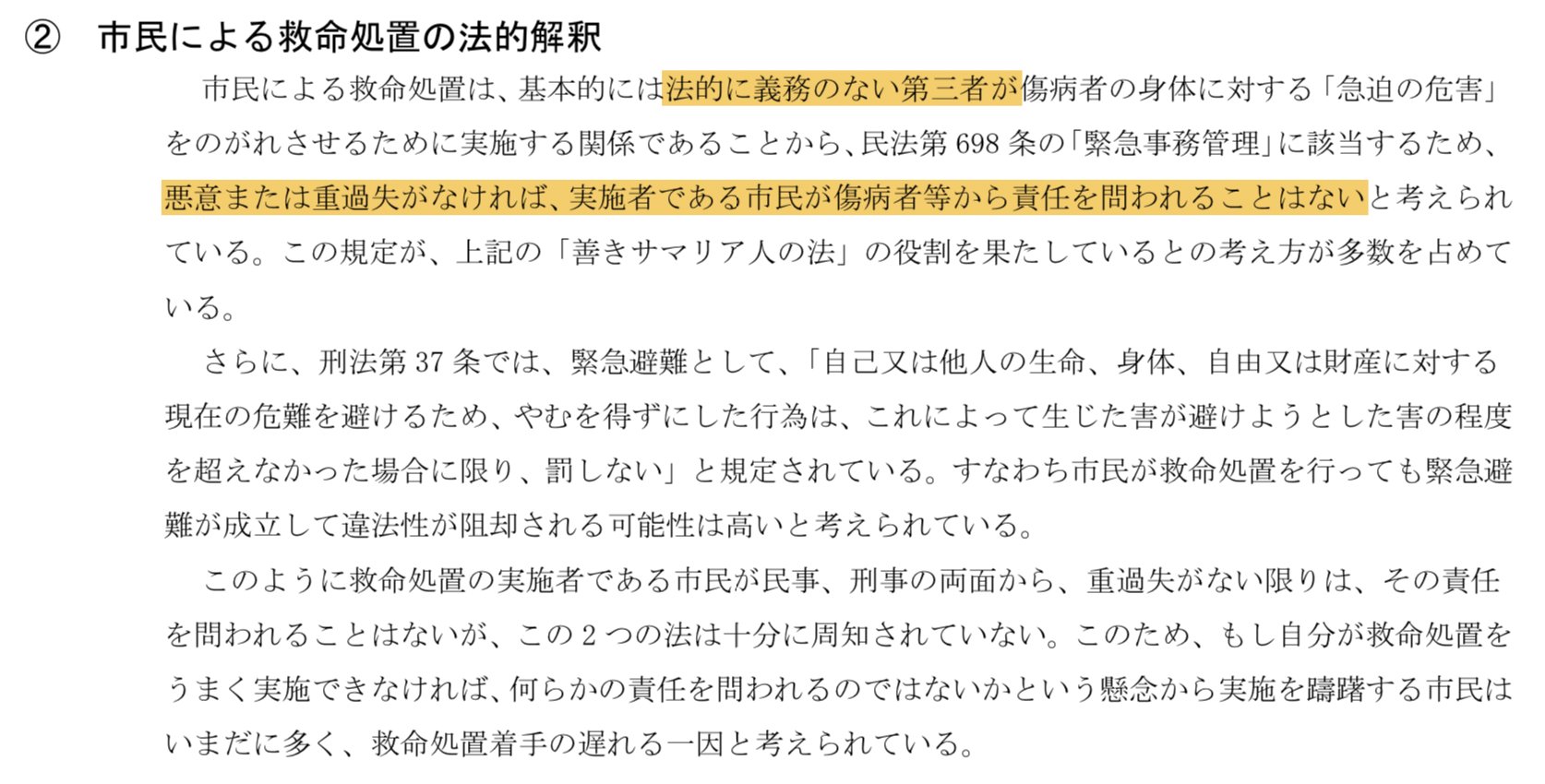人命救助、ときたら「愛と勇気」。
誰もが違和感を感じない言葉の組み合わせだと思います。
実際、救命講習を受講するとたいてい耳にします。
しかし、この背後にあるのは次のような前提です。
・救助の原動力は隣人愛
・不測の事態
こう考えると、「愛と勇気」は同じ救護でも「業務対応」には当てはらまない、という点にお気づきでしょうか?
例えば、救急隊員。
彼らにとって救助行動の原動力に隣人愛もあるのかもしれませんが、それよりはむしろ責務・使命です。
あらゆる事態を想定して備えていますから、勇気というよりは、冷静な判断です。
救急隊員が勇気を主たる原動力として行動しているとすれば、非常に危険です。
もちろんリスクと対峙するときにはいくばくかの勇気は必要ですが、勇気を前提とするとき、その鏡像にあるのは自信のなさ です。
訓練し、自信を高めることで、勇気に依存する割合は減っていきます。
つまり見方を変えれば、勇気に依存した行動というのは、訓練が足りていないのです。
心肺蘇生法講習で、「愛と勇気」と言ったときに違和感を感じない私たちですが、これを救急隊員のトレーニング、医療従事者のトレーニングに持ってくると少しおかしな話になってきます。
愛に基づいた行動というのであれば、そもそも手出ししないという選択肢を秘めています。
しかし業務対応の医療者は、心停止者を目の前にして何もしないという選択肢はないのです。そこにあるのは愛云々ではなく使命だけ。
足がすくんで動けなかった。現実そういうこともあるとは思いますが、それは言い訳になりません。いくら勇気がなくてもやらなくてはいけないのです。そのためには、自信を持てるまでの訓練あるのみ。
世の中、いろんなタイプの救命講習がありますが、講習プログラムの組み立てそのものが、市民向けとプロ向けではまったく違う、という点、ご理解いただけたるでしょうか?
愛と勇気で受講者を送り出す救命講習は、自信という域にまで達することを前提としていないわけです。
この違いは、市民と医療者というくくりだけではありません。
医療資格を持たない市民の立場であっても、学校教職員や保育士、ライフガード、プールの監視員、福祉施設職員などは、「愛と勇気」の人ではないはず。
それが仕事なのですから。
愛と勇気が許されるのは、責任を伴わない人、つまり通りすがりのバイスタンダーだけです。