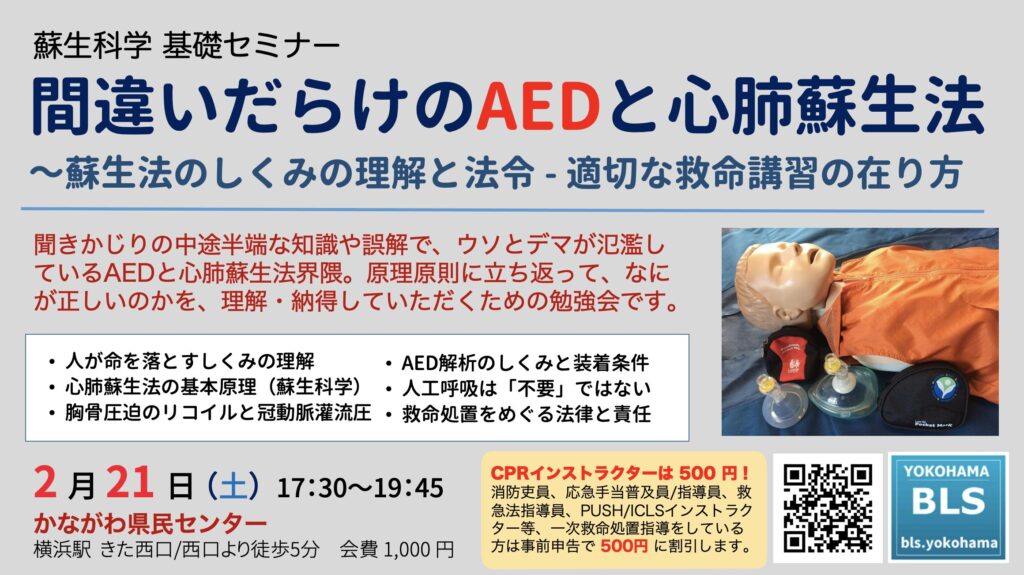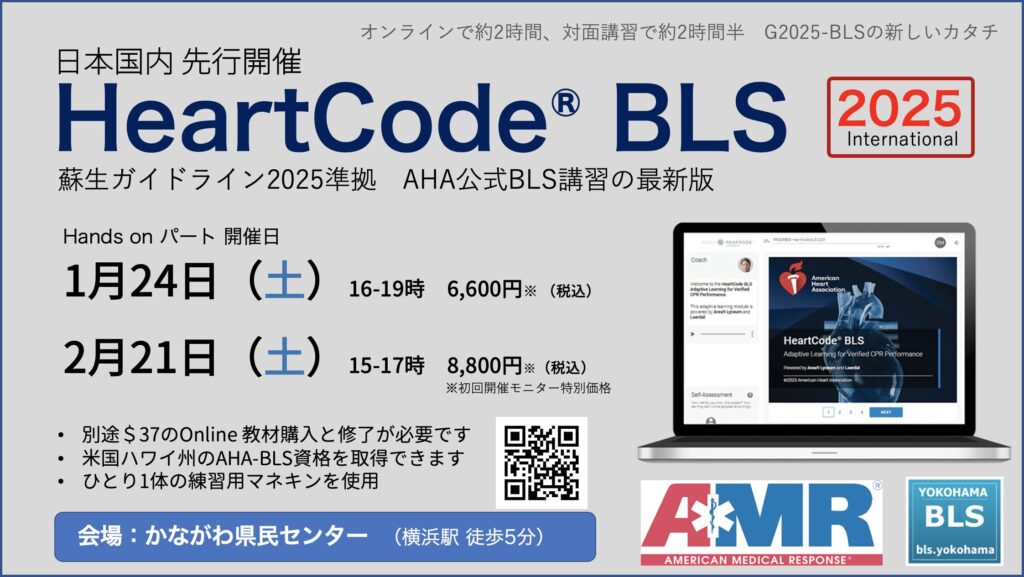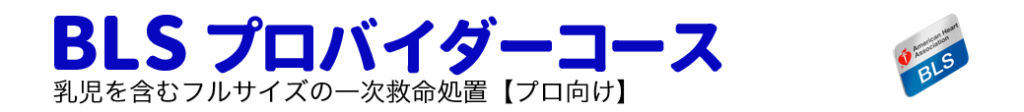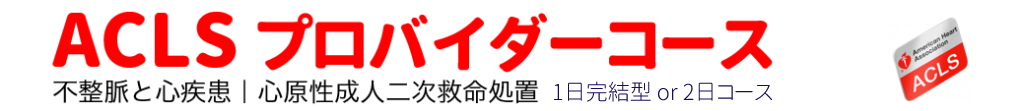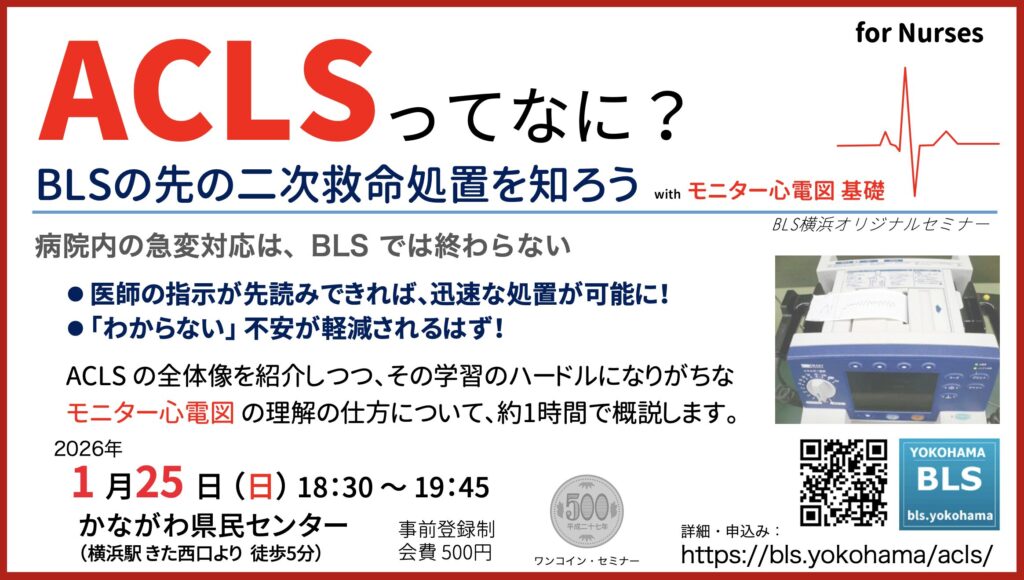心停止したら、二次救命処置で気管挿管するもの。
臨床ではそんなイメージがあるかもしれません。

ACLSプロバイダーコース受講者には、気管挿管を含めたトレーニングを期待して来る方もいらっしゃいますが、実は AHA-ACLSコース の中では、気管挿管の手技は練習項目に入っていません。
挿管はするだけのメリットはありますが、逆にデメリットもあるため、妥当性を検討して判断するように強調されています。
むしろ ICLS に比べて、AHA-ACLS では挿管は急がない、というメッセージ性が強いかもしれません、
気管挿管のデメリット
気管挿管することでのデメリット。それは胸骨圧迫の中断です。
特に AHA は10秒以上の胸骨圧迫中断を避けるように強く強調しており、動画教材の中ではこのように描いています。
・胸骨圧迫を中断せずに気管挿管する
・圧迫を中断する場合は10秒未満とする
・10秒以内に挿管できなければBVM換気に戻る
この中断時間を管理するためにリーダー(医師で挿管する立場と考えてください)とは別にCPRコーチというCPR質管理のサブリーダーを設定して、中断時間を管理するように推奨しています。
胸骨圧迫で体がガタガタと揺れている中での気管挿管が基本となると、この水準で気管挿管ができるのは救急部の医師や日頃やり慣れた麻酔科医くらいかもしれません。
つまり、最初の10分くらいの初動時には、バッグマスク換気が問題なければ挿管を急ぐ必要はないということです。
気管挿管のメリット
気管挿管することのメリットは、非同期式のCPRにできるので、胸骨圧迫の中断時間が減ることが最大のメリットです。
また無脈性電気活動(PEA)で原因が低酸素の場合などは、心拍再開(ROSC)につながる介入としては意義が大きいでしょう。
特に胸骨圧迫の中断が減ると、ROSCとも相関すると言われている胸骨圧迫(CCF:Chest Compression Fraction)の大幅な向上が期待でき、ROSC率改善に繋がります。
また呼気終末二酸化炭素濃度(EtCO2)の測定ができるようになるため、胸骨圧迫の質(10mmHg≧EtCO2)の定性的な評価ができる他、ROSCの検出にも使えます。
EtCO2の活用については、けっこうややこしい話なので下記ページの詳説をご覧ください。

まとめ
胸骨圧迫の中断時間が10秒を超えるというクリティカルなデメリットがない限りは、心停止における気管挿管は有益です。
PEAで、低酸素性の場合や、気道に問題がある場合、嘔吐(胃内容の逆流)のリスクが高い患者には、気管挿管は有益である可能性が高いです。
しかし、例えば心室細動による心停止で、1回ショックをしたあとの2分間のCPRの間で挿管する必然性はほぼないでしょう。(2分間のCPRでROSCすることが期待できるから)
AHA-ACLSのコースのシミュレーションの中で、リーダー(受講者)が気管挿管を指示した場合は、中断時間やCCFの測定結果や推定された原因をもとに妥当性を皆さんで振り返ってもらっています。
実際のところ、挿管しない判断になるケースが多い印象です。
おまけ:NCLSコースでは
とはいいつつも、2025年3月から新しく始めた《NCLS-看護師に必要な新しいBLSコース》では、看護師向けということで気管挿管介助の練習をコース内に組み入れています。
そして、シミュレーションの中でもCPRしながらの気管挿管介助を経験してもらうようにしています。
日本の医療界では妥当性はさておき、CPR中の気管挿管になるケースが多く、看護師にとってはその介助が急変対応の不安要素になっているからです。