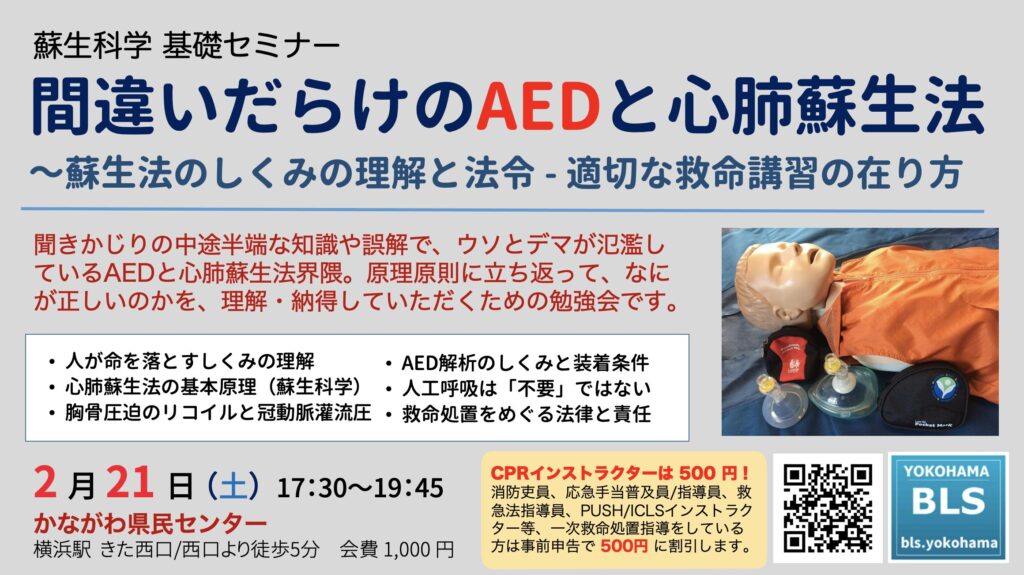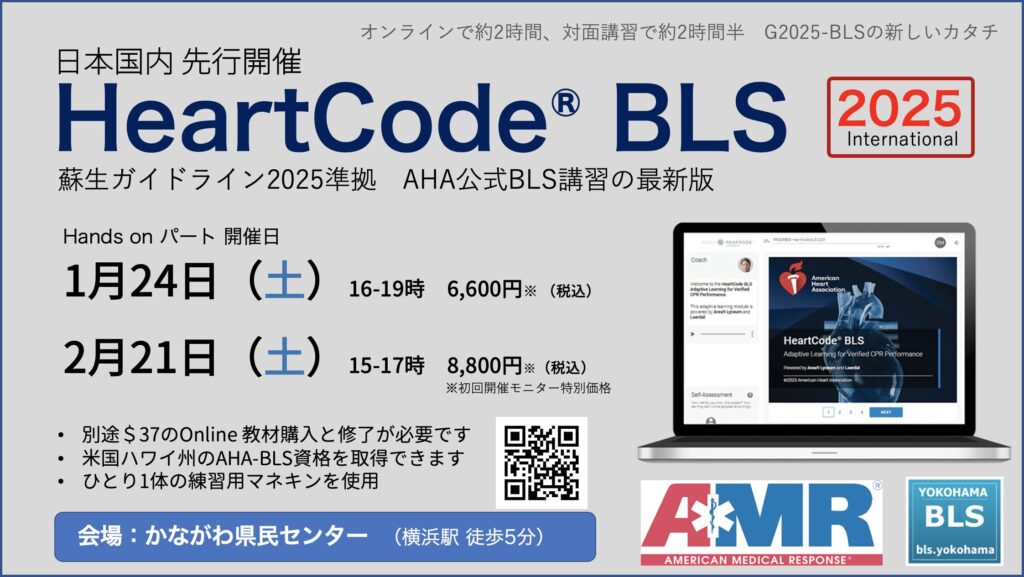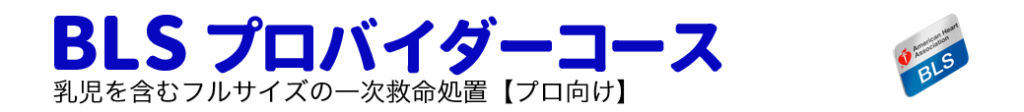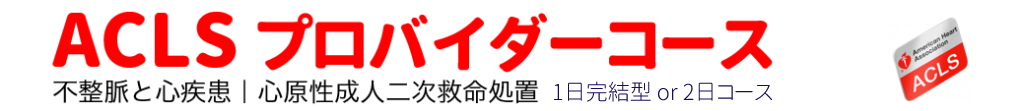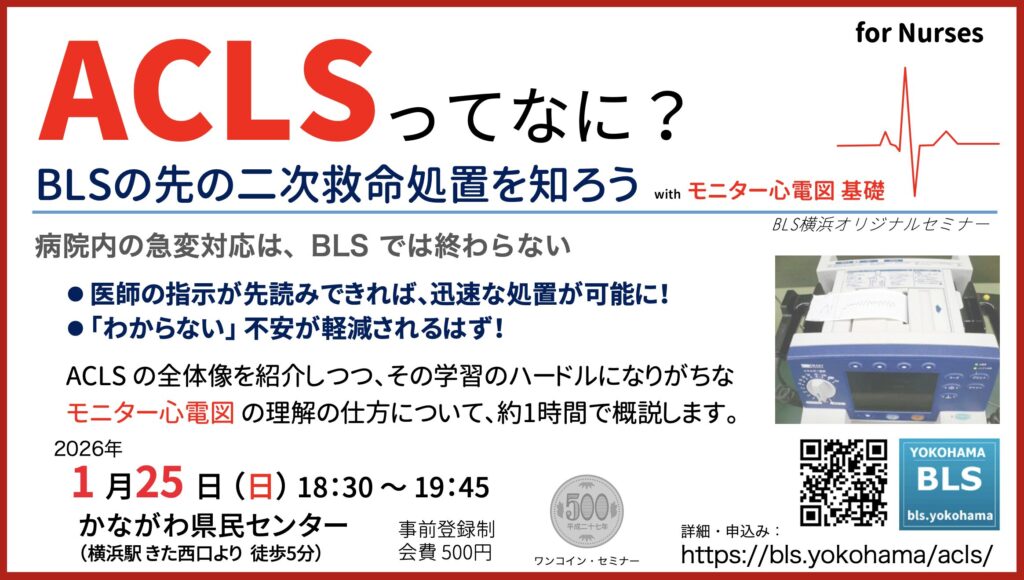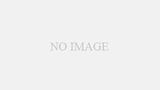10月18日に公開になった新しい心肺蘇生ガイドライン2010を読み込んでいます。
ガイドラインの変更点というと、A-B-Cから、C-A-Bになったとか、「見て聞いて感じて」がなくなったとか、徐脈のACLSアルゴリズムからアトロピンがなくなったとか、そういった末節的な所に目がいきがちですが、実は今回のガイドライン2010では、もっとダイナミックな部分で変化があったように感じています。
蘇生率を向上させるためにどうしたらいいか?
これまではテクニックやスキルとしてのBLSやACLSの手順や方法に焦点が当てられていました。
しかし今回のガイドライン2010は、個人技術の問題から、チームプレーや社会的バックアップ体制へとシフトしてきている点が、全編を通して随所から感じられます。
これまではアルゴリズムやテクニカルスキルに重きが置かれていたACLS/PALSにチームダイナミクスという新たな概念が追加されたのがガイドライン2005でした。
チームとしてのノンテクニカル・スキルに焦点を当てたG2005のACLS/PALSのトレーニングはおおむね良好で、今回のG2010も引き続きチーム蘇生の概念は盛り込まれることになっています。
そして、それが今度はBLSのレベルまで下りてきているような雰囲気を感じます。
というのは、これまでのBLSでは一人法CPRが基本でした。
しかしガイドライン2010では、前提は一人ではありません。その場にいる人を巻き込んで蘇生を行うことが強調されています。一人法はやむをえずの場合、といった位置づけです。
また市民救助者の場合も、一人ではなく、119番通報等で、指示を受けながら呼吸確認を行うようになっていたり、また社会に対しては電話でCPRの指示を出すシステムの重要さが説かれていたりと、これまでは個人技量としてとらえられていたBLSを大きなシステムの一部という図式に改められている点が、今回のガイドラインのキモなのではないかと感じています。
ガイドライン2005は個人への勧告
ガイドライン2010は社会システムへの勧告
こんな視点を持って、ガイドラインを読んでみると、壮大な構想が見えてきます。
行政や組織、地域への課題が大きく突きつけられているガイドライン2010。
町中すべてがICU、というAHAが目指す社会像。
それを具現化するヒントが詰まっています、ガイドライン2010には。