前回の続き、ガイドライン2010の呼吸確認の変更をどう教えるか、という話です。
G2005: 気道確保+「見て聞いて感じて」
↓
G2010: 気道確保なし、胸から腹の動きを「見る」
まず、これを大きな変更ととらえるか、ちょっとした変更ととらえるか、また改善されたと考えるのか、ある意味改悪と考えるのか?
まずはインストラクター自身の、理解・意識が重要です。
これまで自信をもって、気道確保の重要性を説いていた指導員からしてみれば、あっさりと廃止されてしまって、これまで教えていたことを全否定されたような印象を受ける方もいるかもしれません。
舌根沈下があるから、気道確保しなくては呼吸の有無はわかるわけがないと考える人もいるでしょう。
まずは、インストラクターが自信を持って新しい呼吸確認法を人に推奨できるか、そこが問題かと思います。
こんなあたりを、指導に当たる皆さんで考えてもらえたらと考えていました。
考える上でのヒントは、「死戦期呼吸」そして「実行性 implementation」。それを踏まえたうえで、
・「見て聞いて感じて」のデメリットは?
・呼吸確認の前に気道確保を教えた場合のデメリットは?
を考えると、自信をもって指導ができるようになるのではないでしょうか?
さて、指導の実際ですが、ただ見るだけ、5秒~10秒かけて、というのは、やっている人の気持ちとしては落ち着かないものです。
もともとマネキンの胸が動くわけがないと思っているものですから、この練習時間に耐えられない。それをいみじくもカバーしていたのが「見て聞いて感じて」というお作法でした。
「見て、聞いて、感じて、4、5、6、7、、、、」
と声に出していうことで、空虚の溝を埋めていた、といったら皮肉が過ぎるでしょうか?
ガイドライン2010になって、手を出さず、ただ胸を見るだけの10秒間。
これを納得してもらうには、マネキン相手の練習だけでは不十分かもしれません。
私たちは、この場面には生体を使った練習を取り入れています。
インストラクターが床に寝て、呼吸あり、呼吸なしをランダムに繰り出して、それを判断してもらう練習。
これから日本国内の他団体もガイドライン2010に移行するにつれて、このあたりの指導ノウハウは色々でてくると思います。
それに先駆けて、グループディスカッションの中から、いろいろな思案が出てきたら面白いなと思っていました。

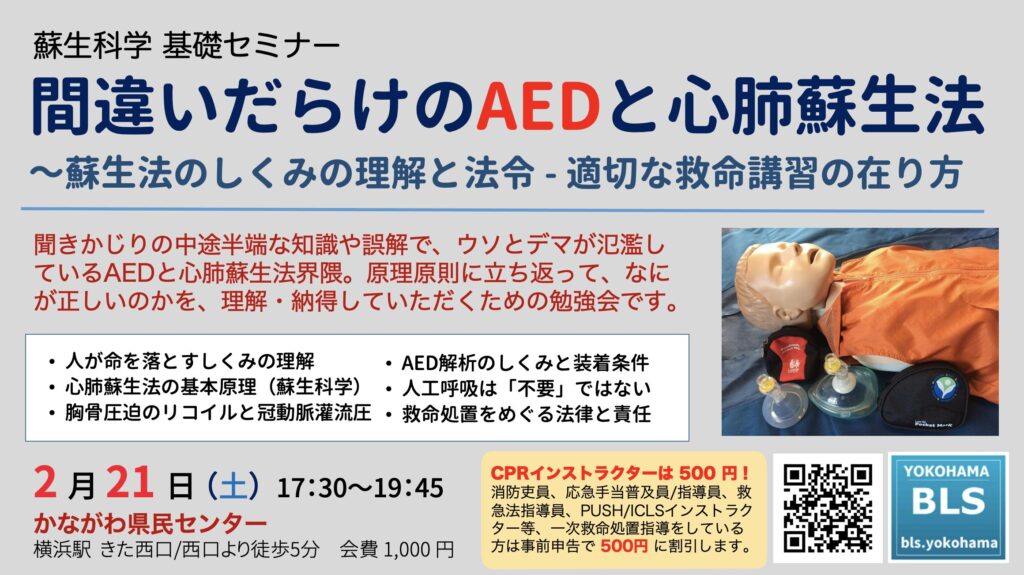
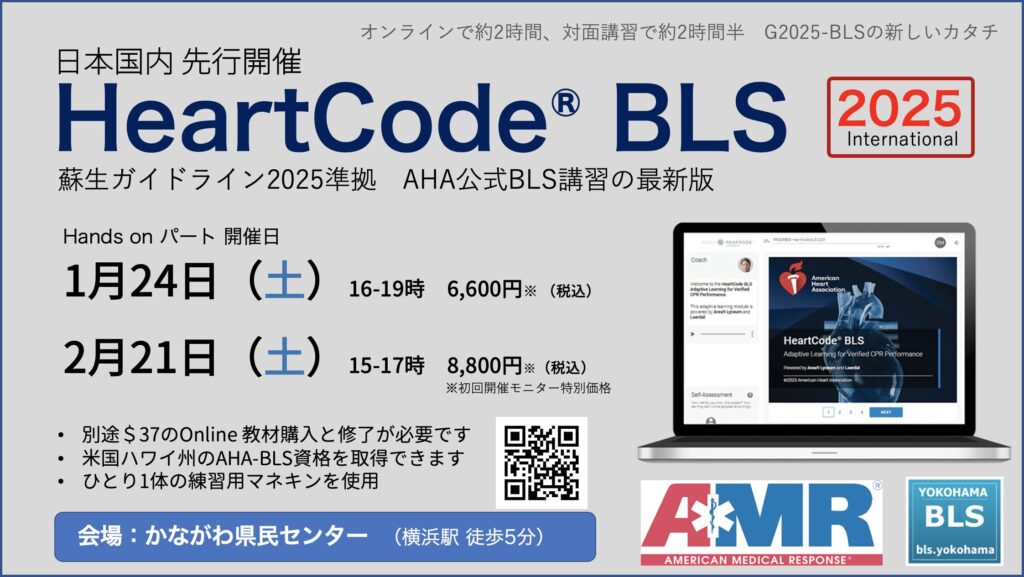
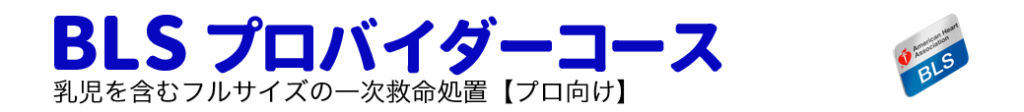

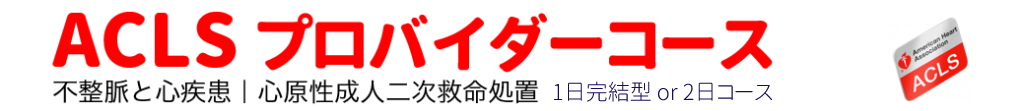
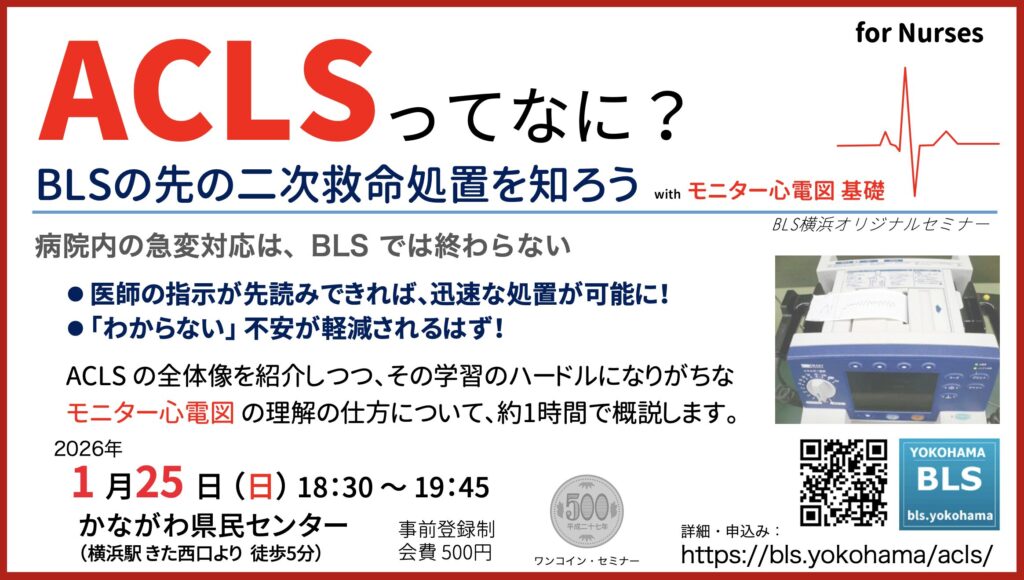
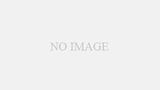
コメント
もう既に幾度となく受講者同士で寝っ転がってお腹と胸の動き、うつ伏せでの背中の動き、横向きでの体の動きを体験して貰っています。
ただね、例えば会場が畳の上とか参加者全員が作業着だとか、男性女性の割合が半々もしくはどちらか一方な時は出来るのですが、あまりそう云った好条件の講習会は無いんですよね。
インストが寝っ転がればいいのですが、説明しつつ息を止めるって至難の業ですし。
実際、仰向けに倒れている人ってあまり居ないんですよね。
胸骨圧迫ありきの講習会なんです。
それはそれで、胸骨圧迫とAEDを安全に使う練習の目的としては良いと思います。
でもね、反応の確認と呼吸の確認をしっかり行い、どちらも無い、もしくは良く解らないという状態で次のステップへ進む訳でして。
しっかりと自身の安全を確保しつつ、呼吸の確認が出来ると言った所で、G2010の変更はよりやり易くなったのかと感じます。
別に見て聞いて感じてをやればいい訳ですので、実際はスキルや状況によって使い分けても良いのだと思います。
それを”見て聞いて感じては必要ありません”なんて言った時には、それこそ”お作法講習会”になってしまいます。
なぜ省かれたのかを理論的にきちんと説明する事が非常に大切です。
ガイドラインが変更になったから・・・
コレって、説明になっていませんよね。
その為にも、しっかりとガイドライン類を熟読してその背景等も含めてしっかりと理解する必要があります。
バダンという音を聞き付け隣の部屋に見に行ったら
男性が俯せに倒れてる
声かけ、観察で息をしていないと驚き
男性を仰向けにし、顎を持ち上げたときに大きく呼吸を開始
多分今後そういう場面に遭遇したとしても
気道確保はするかもしれない…
それを『間違いだ』と明確に説明してくださるお方がいらっしゃらない限りは
まささん、コメントありがとうございました。
おっしゃるとおりこれまでは心停止ありきの講習会がメインでした。その点、生身の人間で呼吸確認までの流れを練習すると、バリエーションが出てきます。目を閉じていたけど、声をかけたら目が開いたとか、意識はないけど呼吸は正常にしている、とか。
この部分は私たちは「ファーストエイド」の範疇と捉えて、ファーストエイド講習で練習してきましたが、今後はCPR講習の中でもきちんと体験してもらったほうがいいのかなとも考えています。
最悪の事態である心停止の対応だけでも極力シンプルに教えるべきというのがG2005の潮流ですが、G2010の精神からすると、現実に対応できる力をつけるという方向性も加味すべきなのかなと思慮中。
とらにゃんさん、はじめまして、でよろしかったでしょうか?
間違いだとの明確な指摘、というのはないと思います。
これまで絶対神話のように思われていた蘇生ガイドラインですが、G2010では、日本版ガイドライン、米国版(AHA)ガイドライン、ヨーロッパ版ガイドライン、オーストラリア版ガイドラインなどで、それぞれ内容が違っています。
C-A-Bに変わったのは日本とアメリカだけで、ヨーロッパなどはG2005から変わらずA-C-Bですし。
知識がある人は、自分で考えてその場にあった手順で行動しましょう、というのがG2010時代のメッセージです。